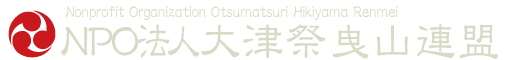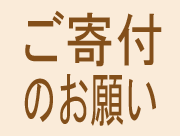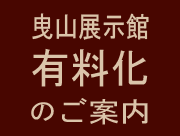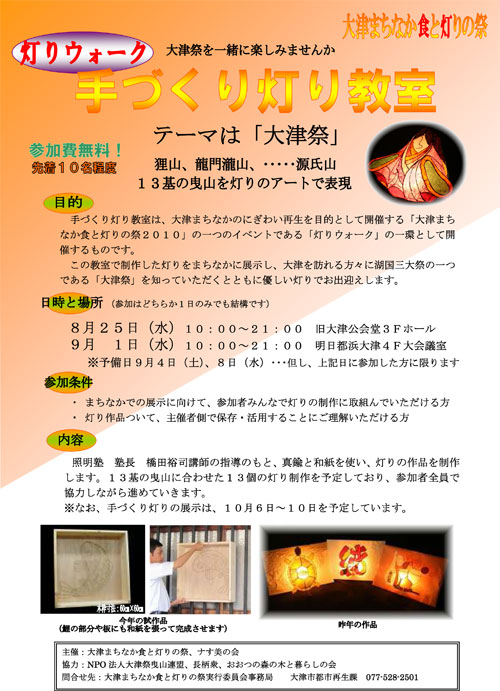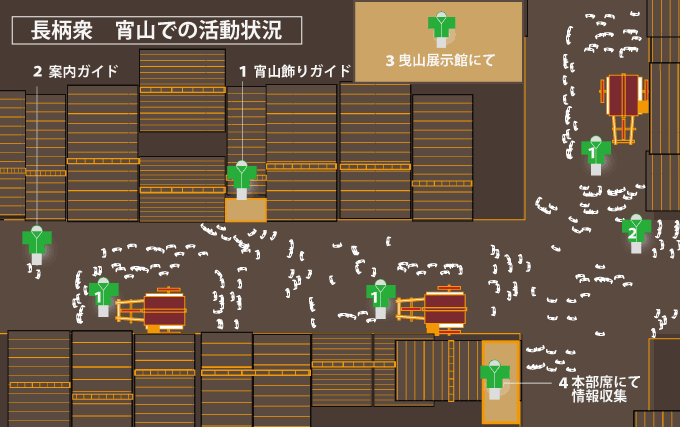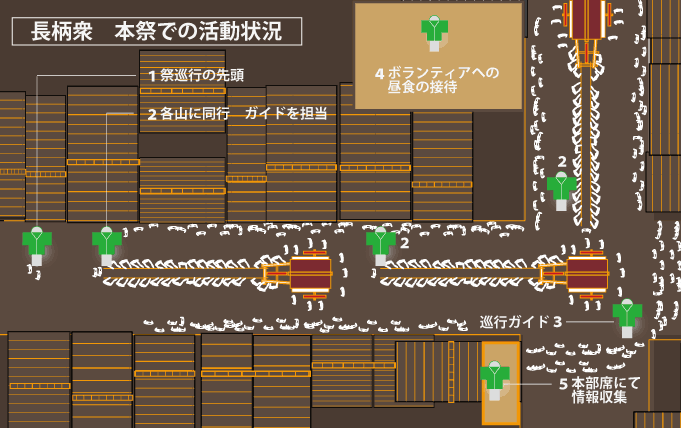『第3回長柄衆の集い』
◆日時 :平成22年8月22日(日) 13:30〜17:00
◆場所 :大津祭曳山展示館3F多目的ホール
◆内容 :1.講話「大津祭の似合う街づくり」 大津祭曳山連盟理事長 白井勝好氏
2.大津祭役割分担
「長柄衆の集い」は、はや第3回を迎えました。
今回の研修は、特別講師として、おなじみの大津祭曳山連盟理事長 白井勝好さんにお越し頂き、「大津祭の似合う街づくり」をテーマに講話を頂くことが出来ました。
冒頭では、曳山連盟がNPO法人化の道を選択し現在の形に進化してきた経緯を中心にお話いただき、まだまだ新参者の私としても非常に興味を持って受講することが出来たし、また、有意義な時間が過ごせたと思います。
行政サイドとしての大津市は、大津の街並みを中心市街として活性化させようという意向で、曳山連盟としてはこれをフォローするかたちで精力的に活動しているようです(曳山連盟のネームバリューを活かして、活動を展開するほうが何かとコトが進みやすいなど)。
このなかでは、「行政よりの支援」と連携、「まちづくり大津」との連携、各種団体よりの支援と連携、「大津祭ちま吉協議会」、など多岐に渡る活動が展開されており、我々長柄衆との連携もこの一部に位置付けされています。
具体的活動事例として、「大津町家再生事業」としては、立命館大学の調査により約1,600軒の町家が残っているらしく、これらの再生事業が既に具体化しつつあるようですが、この進捗にも曳山連盟が深く関わっており無くてはならない存在になっているそうです。
また、「まちづくり大津」の活動支援としては、既に営業を開始している「なぎさのテラス(なぎさ公園内)」、浜大津アーカス内「湖(うみ)の駅」などが、身近なものとしてあります。次期活動として、東海道筋の整備に着手するそうで、具体的には京町通を中心に「電柱の排除(地中に埋めるなど)」を検討中とのことでした。各町家との100%のネゴシエーションが必須となるため曳山連盟の活動に大きな期待が掛かっているということですね。
「ちま吉協議会」との連携では、ちま吉デザインの飲料水自動販売機の導入を検討してきたそうですが、あまり今までうまく進まなかったという話をして頂きました。ところが、最近、コカコーラさんからオファーがあり、やっと理解が広まってきたことを実感できつつあるようです。気になる1号機の設置は、曳山展示館内を考えているらしいので皆さん楽しみにしておいて下さい。10台くらい設置できたら、それだけでかなりの収入が期待できるそうで、さすがの白井理事長もちょっと不気味な笑みを浮かべておられました。我々長柄衆にも、なにかフィードバックがあれば良いですね。
私たちもお世話になってきた「大津まちなか大学」ですが、龍谷大学や立命館大学といった地域の大学から、提携のオファーがあり「大津祭」をキーワードに、新風を取り入れてゆく方針です。一方で、大津祭の伝統的な文化継承との両立をはかりながら、進めていきたいという意思を(白井さんは)表明されていました。
他にも、多岐にわたる活動を展開されており、上記は、本日講義をして頂いたなかの一部です。本当に多岐にわたる現在の活動は、ご自身も「まさかこんなことになるとは思っていなかった(大津祭のことだけ活動するつもりだった)」とおっしゃるほど。(実は、曳山連盟のHPに、詳細な活動紹介がありますので、気になる方はココで復習できますよ)
伝統的な大津祭の継承と、講義いただいたような大津の活性化と、この2つを有機的に織り交ぜながら魅力的な街づくりを展開していって欲しいと感じました。また、私たち長柄衆としても、連携を密にとり積極的な活動をしていきましょう。
2010年08月22日
まちなか大学4期世話人 長澤 智